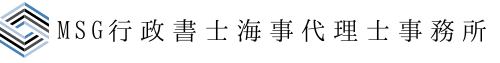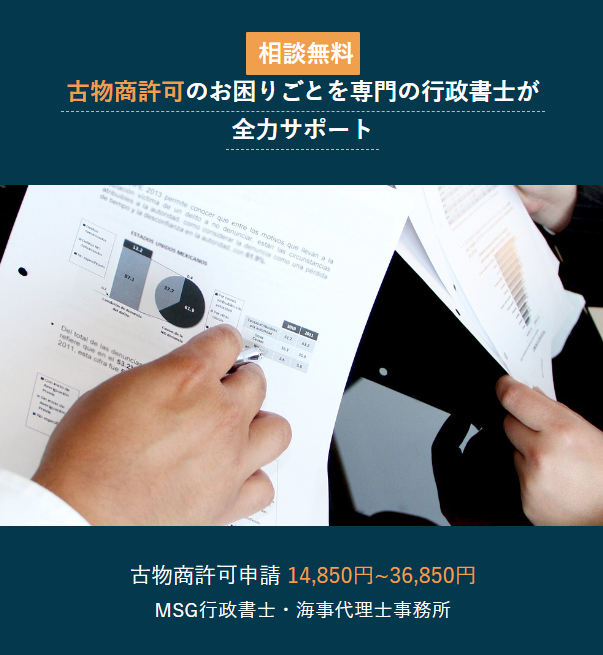建物や構造物を取り壊して更地にする「解体工事」は、年々ニーズが高まる一方で、法規制が非常に複雑な分野でもあります。
とくに、解体業を営むにあたっては「建設業許可が必要なのか」「解体工事業登録だけで足りるのか」など、制度の違いが分かりづらく、事業者が悩むポイントの一つです。
本ページでは、2025年時点の最新制度に基づき、解体工事業に必要な建設業許可について紹介します。
解体工事業に建設業許可が必要な場合
解体工事業は、建設業法に定められた29業種のうちの1つで、平成28年6月より、とび・土工工事業とは別の独立した業種として新設されました。
従来、建物の解体工事は「とび・土工工事業」の許可で対応可能とされていましたが、明確に区分されることとなりました。
500万円以上は許可が必要、500万円未満は解体工事業登録のみ
このため、現在では一定規模(請負代金が500万円以上)の解体工事を請け負うには、建設業許可が必要です。また、建設業許可が必要ない(請負代金が500万円未満の解体工事)場合であっても、建設リサイクル法に基づき「解体工事業登録」が必要となります。
解体工事とは具体的に
建設業許可における解体工事とは、「工作物の解体を行う工事」を指します。
たとえば、下請として「一戸建て住宅を取り壊して更地にする」工事を、500万円以上で請け負う場合には、建設業許可としての解体業許可が必要です。
ただし、特定の専門工事で建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。つまり、例えば、「信号機を解体して同じものを作る」工事や「信号機を解体して更地にする」工事の場合には、電気工事となります。
さらに、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当するため、例えば元請として「一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る」場合には、建築一式工事に該当します。
このように「解体」が伴うからといって必ずしも、建設業許可のうち解体工事業が必要ではありません。
| 解体を伴う新設 | 解体のみ | ||
| 例)電気工事による信号機を解体して同じものを作る | 例)建築一式工事による一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る | 例)電気工事による信号機を解体して更地にする | 例)一戸建て住宅を壊して更地にする |
| 電気工事 | 建築一式工事 | 電気工事 | 解体工事 |
建設業許可(解体工事業)を取得するための主な要件
経営業務の管理責任者に関する要件
建設業許可の取得にあたっては、経営業務の管理責任者を置く必要があります。
この経営業務の管理責任者の要件にはいくつかの類型がありますが、以下では比較的多くのケースに該当する代表的なパターンを紹介します。
- 建設業に関し5年以上の経営経験がある
例)建設業を営む株式会社・有限会社の取締役、個人事業主としての経験等が当たります
証明書類についてのよくある質問
- 解体業を営む株式会社(建設業許可あり)の取締役として5年以上の経験があります。この場合、どのような証明書類を用意すれば良いでしょうか
-
建設業許可をおもちの会社ですので、建設業許可通知書のコピー等を用意するとともに、役員期間が把握できる履歴事項全部証明書を用意する必要があります。
- 解体業以外の建設業を営む個人事業主として5年以上の事業経験があります。この場合、どのような証明書類を用意すべきでしょうか。
-
この場合、所得税の確定申告書の写し、期間分の建設業に関する工事請負契約書・注文書又は請求書等の写しなどを用意する必要があります。
専任技術者に関する要件を満たす
各営業所ごとに専任技術者を1人配置することが義務付けられています
下記の①~③のいずれかを満たす者を営業所ごと一人常勤で配置しなければなりません。
- 一定の国家資格を有している
(下記、代表例)- 1級土木施工管理技士 ※1
- 1級土木施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級土木施工管理技士(土木) ※1
- 2級土木施工管理技士補(土木)(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装、薬液注入)(実務経験5年)
- 2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装、薬液注入)(実務経験5年)
- 1級建築施工管理技士 ※1
- 1級建築施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級建築施工管理技士(建築、躯体) ※1
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)(実務経験5年)
- 2級建築施工管理技士補(実務経験5年)
- 1級造園施工管理技士(実務経験3年)
- 1級造園施工管理技士補(実務経験3年)
- 2級造園施工管理技士(実務経験5年)
- 2級造園施工管理技士補(実務経験5年)
※1:平成28年度以降に合格した者、または 平成27年以前に合格して解体工事に関する実務経験1年以上 または 登録解体工事講習を受講した者
- 解体工事業の実務経験が10年以上ある
- 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- 指定の学科卒(土木工学又は建築学)+解体工事業の実務経験がある
- 大学・高専・短大の指定学科卒の場合は3年以上の実務経験のある人、中等教育学校、高等学校、専修学校の指定学科卒の場合は5年以上
建設業許可と併せて検討すべき手続き
解体工事業登録
建設業許可を取得していない場合でも、解体工事を請け負うには「解体工事業の登録」が必要です。
元請・下請を問わず、500万円未満の解体工事を行う場合でも、工事を行う都道府県ごとに登録が義務付けられています。
ただし、建設業許可(解体・建築一式・土木一式)を保有する方は登録を必要ありません。
産業廃棄物収集運搬業の許可
解体に伴い発生した廃材や廃棄物を自社で運搬する場合には、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
運搬は委託する場合も多いため、自社で廃棄物を運ぶかどうかを判断基準に検討しましょう。
解体工事業の許可申請は行政書士にお任せください
解体工事業の建設業許可や関連手続きには、法令に基づく正確な書類作成と要件の確認が求められます。
当事務所では、建設業許可に精通した行政書士が、丁寧かつ迅速に対応いたします。
ご依頼、ご相談はお気軽に下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。