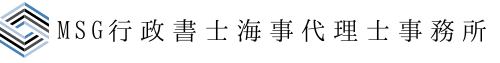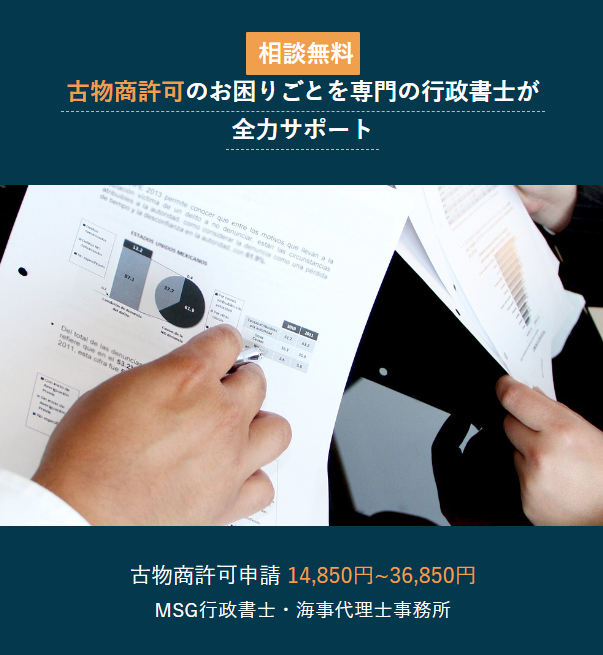「軽微な建設工事」以外の電気工事を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず必ず建設業許可を取得しなければなりません。
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基盤の三つ要件を中心に解説いたします。
電気工事業とは?
建設業許可の「電気工事業」とは、「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」を指します。
具体的には、以下が建設業許可の手引きに例示されています。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事(避雷針工事)
- 太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの) ※屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」に該当
一件の請負代金が500万円未満であれば建設業許可は不要
建設業においては、1件の請負代金が500万円未満の工事は「軽微な建設工事」とされ、この範囲であれば建設業許可は原則不要です。これは、公共工事・民間工事を問わず共通のルールです。
しかし、電気工事業の場合には注意が必要です。
たとえ500万円未満の軽微な電気工事であっても、その工事が電気工事士法に基づく「電気工事」に該当する場合には、電気工事業の登録手続きが必要となります。
このように、建設業許可と電気工事業の手続きを並行して考慮する必要があり、それぞれの制度に対応した手続きが必要です。例えば、現在登録電気工事業者となっている事業者が、建設業許可を取得された場合には、登録の効力を失うため、みなし登録電気工事業者の届出が必要となります。
経営業務の管理責任者を一人選任する
電気工事業で建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者」を1名選任する必要があります。
この要件は、一般的に 5年以上の建設業の経営経験を証明することで満たすケースが多い です。
以前は、建設業29業種のうち、許可を取得したい業種での経営経験が求められていました。しかし、法改正により要件が緩和され、現在は 「建設業に関する経営経験が5年以上あれば、業種を問わず認められる」 ようになりました。
法人の場合は 常勤役員、個人事業主の場合は 本人または支配人 のうち1名を選任し、要件を満たしていることを証明する必要があります。
| 要件 | 許可の有無 | 証明方法 |
|---|---|---|
| 建設業を営む会社で5年以上の役員経験がある | 建設業許可あり | ・建設業許可通知書のコピー ・履歴事項全部証明書 |
| 建設業許可なし | ・「工事請負契約書」「注文書」「請求書」など ・ 「履歴事項全部証明書」 | |
| 個人事業主として5年以上建設業を営んでいる | – | ・「工事請負契約書」「注文書」「請求書」など ・5年以上の「確定申告書(原本)」 |
補足: 複数の法人や業種における役員経験や事業経験を合算して証明することも可能です。ただし、証明書類の準備には時間を要する場合があるため、事前に必要な書類を確認し、早めに手続きを進めることをおすすめします。
一般的には、上記の要件を満たすことで認められるケースが多いですが、執行役員としての経験や、一定の経験を持つ補佐者を配置することで要件を補う方法もあります。
専任技術者を一人選任する
建設業の許可を取得するためには、各営業所ごとに専任技術者を1人以上配置することが義務付けられています。
専任技術者は「常勤している」必要があるため、自社の人間であることが求められます。そして、他の法令で専任性が求められる管理建築士や宅地建物取引士などと兼務することは基本的にはできません。
また、基準を満たせば、「専任技術者」と「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」を1人で兼任することも可能です。
電気工事業の場合、以下の国家資格を持つ者であれば専任技術者に選任することができます。電気工事業の場合、資格を保有していなければ電気工事に従事できないことから、無資格者の実務経験で専技の要件を満たすことはできません。
- 一級電気工事施工管理技士
- 二級電気工事施工管理技士
- 技術士法の建設・総合技術監理(建設)
- 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
- 総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)
- 電気工事士法の第一種電気工事士
- 電気工事士法の第二種電気工事士(3年以上の実務経験が必要)
- 電気事業法の電気主任技術者(5年以上の実務経験が必要)
- 建築設備士(1年以上の実務経験が必要)
- 1級計装士(1年以上の実務経験が必要)
財産的基盤・誠実性の要件
建設工事を開始するには、資材の購入や労働者の確保、機械・器具の調達など、一定の準備資金が必要です。
さらに、営業活動を行うためにも、ある程度の資金を確保しておく必要があります。
そのため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うには、十分な財産的基盤を有していることが求められます。
具体的に財産的基盤を証明するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本の額が500 万円以上あること
- 500 万円以上の資金調達能力があること
これは具体的には、以下のアやイの方法によって証明を行います。
① 法人では、申請時直前の確定した貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額をいい、個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
②申請者名義(法人である場合は当該法人名義)の口座における取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書により判断します。
まとめ
電気工事業で一般建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者の要件」「専任技術者の要件」「財産的基盤の要件」など、さまざまな条件をクリアする必要があります。
特に、証明書類の準備や申請書の作成には細かなルールがあり、手続きをスムーズに進めるためには事前の準備が欠かせません。
また、許可取得後も定期的な更新などの手続きが必要になるため、長期的な視点での管理も重要です。
「申請に時間をかけられない」「手続きに不安がある」 という方は、行政書士に依頼することでスムーズかつ確実に許可を取得できます。当事務所では、書類作成から申請代行、アフターフォローまで、電気工事業の建設業許可取得をフルサポート しております。
| 証紙代等 | 基本料金(税込み) | |
|---|---|---|
| 一般建設業許可(個人・知事) | 90,000円 | 99,000円~ |
| 一般建設業許可(法人・知事) | 90,000円 | 110,000円~ |
| 証紙代等 | 基本料金(税込み) | |
|---|---|---|
| 一般建設業許可(個人・大臣) | 90,000円 | 190,000円~ |
| 一般建設業許可(法人・大臣) | 90,000円 | 190,000円~ |
※役員数、経管・専技の証明方法、営業所の数など、難易度によって基本料金に加算額が生じます。
※登記簿謄本、身分証明書等の実費分が発生いたします。
お見積り、ご相談は以下からお気軽にお問い合わせください。